トーク
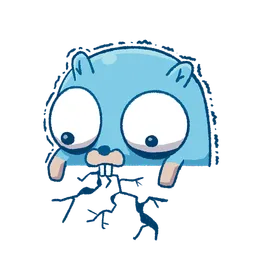
なぜGoのジェネリクスはこの形なのか? - Featherweight Goが明かす設計の核心
Room 1 16:00 - 16:20
Go 1.18でジェネリクスが導入されました。本セッションでは、その仕様、特に「なぜ型制約にinterfaceを使うのか」「なぜコンパイルにモノモーフィゼーションという手法が選ばれたのか」という設計上の選択について、その背景を解説します。
この設計の背景には、Goジェネリクス設計の根幹をなす理論的支柱、Featherweight Goという論文があります。この論文は、Goの父であるRob Pike氏や、Haskellなどで知られる型理論の権威Philip Wadler氏らが参加し、Goのジェネリクスに「理論的な正しさ」を与えるために行われました。この論文で示された理論的な裏付けが、初期案であったcontractsから現在のinterfaceベースの仕様へと繋がりました。
このセッションでは、Featherweight Go論文を基に、Goのジェネリクスの仕組みを深掘りし、以下の点をお話しします。
- interfaceが型制約として採用された経緯(contracts案との比較)
- モノモーフィゼーションの仕組みと、それがもたらす性能上のメリット
- 現在の仕様では実現できない「共変レシーバ」と、それが解決する「式問題」の解説
このセッションを聞くことで、Goのジェネリクスがなぜ現在の仕様になったのかを深く理解し、そのトレードオフを意識した上で、より自信を持ってコードを書けるようになります。